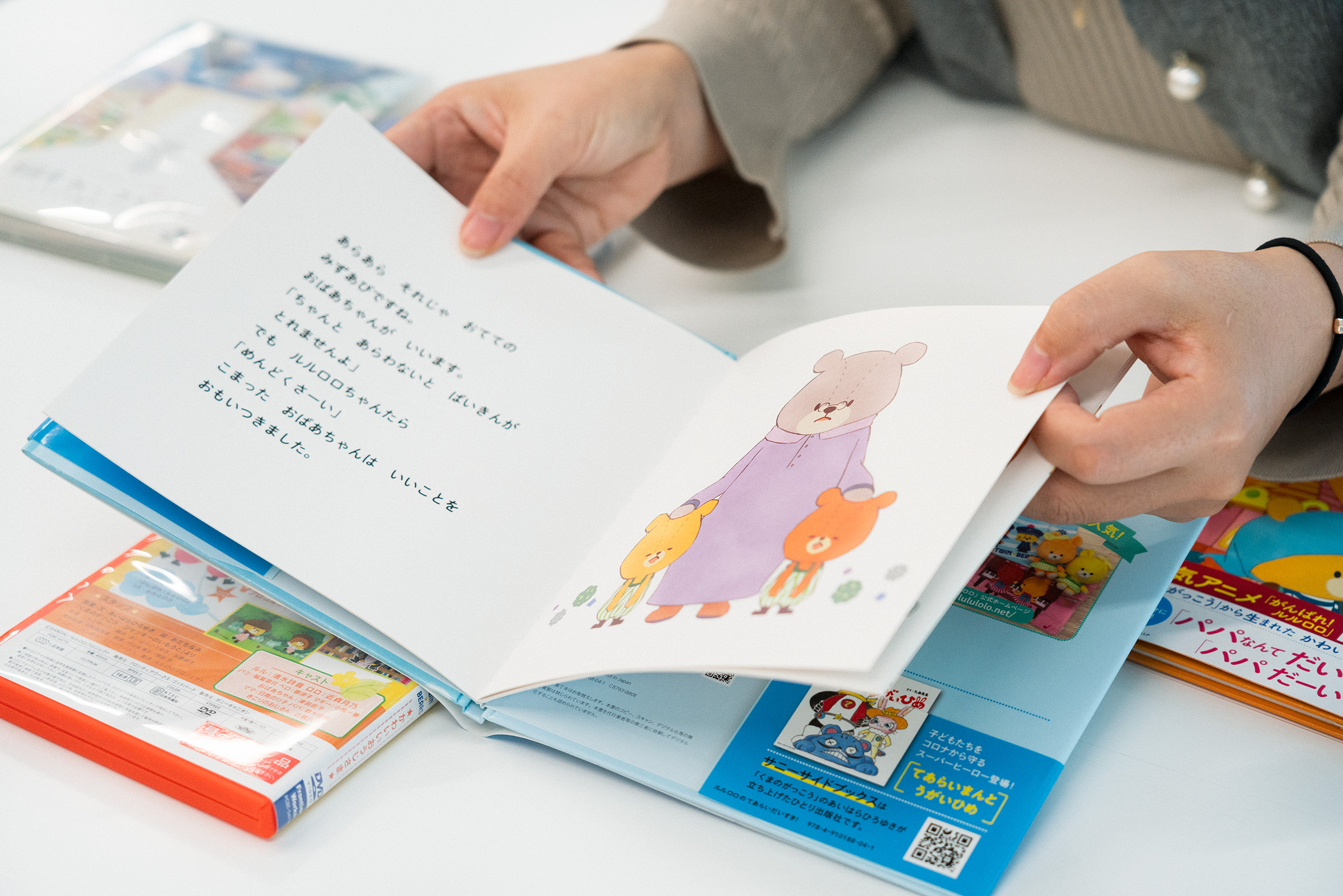チェコのアニメに衝撃を受けた高校生時代
世界でも有数の「アニメ大国」と呼ばれるこの国で、アニメーションの仕事を志すのは自然なことだ。映像ディレクターの松井久美さんもそんな一人だ、と言いたいところだが、話を聞くとどうも勝手が違う。
チェコのアートアニメーションとの出会いから物語が始まるからだ。
松井:アートアニメーションには、原作やキャラクターがあらかじめ存在するのではなく、作家独自の世界観が表現されているんです。風刺だったり、時にはグロテスクだったりと表現に富んでいて、話が難解なものも多い。難解に見えて単純なものもありますし、子供向けの作品もあります。ただ、あまり一般ウケはしないし、そういう作品を好む人も周りにいませんでした(笑)。
感銘を受けたのは、立体のコマ撮りなどの表現手法です。アニメは日本だけじゃないと気づきましたし、私も制作したいと思うようになりました。そこからレンタル店に通い、御茶ノ水にあるマニアックな店にも行きました。高校生には怖い感じのお店でしたが(笑)。インターネットなどで調べながら、独学でアニメーションを作るようになりました。
衝撃を受けたのがヤン・シュヴァンクマイエル(1934〜)の作品だった。なかでも印象深かったのは長編アニメ『アリス』(1988年)。
松井:原作は『不思議の国のアリス』です、実写を交えながらシーンがコマ撮りされています。たとえば、アリスがウサギを追いかけるシーンで、使われているのは剥製のウサギ。胸元から懐中時計を取り出すときに、お腹に詰まったオガ屑が出てしまうのですが、自分で拭き取って時計を見る。ファンタジーと現実をミックスするような表現に驚きました。
2004年、東京工芸大学芸術学部アニメーション学科に入学するのだが、当初は同級生との志向の違いに戸惑いもあったようだ。
松井:でも、工芸大へ来て良かったと思いました。当時の厚木キャンパスでは、実習室の名前にアートアニメーションの作家の名が冠されていたんです。先生たちが目指すところはアートアニメーションを礎にしているんだと感じて、すごく心強かったです。カリキュラムも幅広くて、作品もたくさん見られましたし、コマ撮りやクレイ(粘土)、切り紙を使った表現技法を講義で学べました。さらに同級生から自主グループ制作を誘ってもらうなど、作画アニメにも興味が湧き、結果的にアニメーション制作の手法を一通り経験ができました。
そして迎えた卒業制作のタイミング。壁にぶつかった。
松井:自分の作家性をどう表現しようかと企画段階でかなり悩みました。そこでわかったんです。私はお話を作るのが苦手なんだ、と。
そこで目をつけたのが、宮沢賢治の「やまなし」。自然の美しさと厳しさをテーマにした短編小説の映像化を考えたのだ。独特の擬音が気に入ったという。
5分程度の短編映像は「切り紙アニメーション」で制作された。
松井:水彩紙で関節ごとに描き、切り分けたパーツの裏側に針金を仕込み、カニが動くようにしました。背景には濃淡のある水彩画。カニを少しずつ動かしたり、背景を差し替えたりしながら地道に写真を撮るんです。作画を使ったアニメーションだと、1秒に12枚も絵が必要になるうえ、テレビアニメのような仕上がりになりがちなので、ここでは質感を重視して切り紙を選びました。
この作品は卒業制作の優秀作品の一つとして上映されるなど、校内で高い評価を得た。